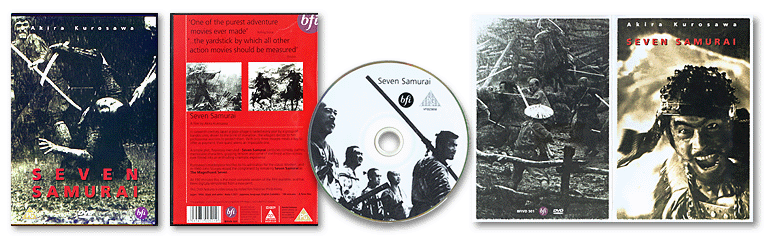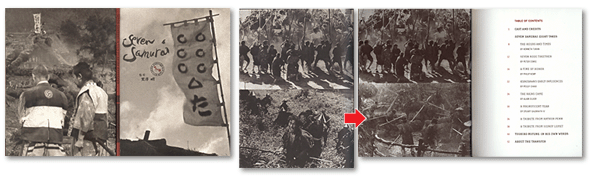------------- ●マッキントッシュ版の方は、Microsoft Internet Explorer5.1のご使用を推奨します ------------- ●ウィンドウズ版の方は、Microsoft Internet Explorer4.01以上、Netscape Communicator4.05以上をご使用ください ------------- ※このまま見続けたい方は一度 →ジャケット比較トップ に戻ってから各ページをご覧ください。 |
|
|
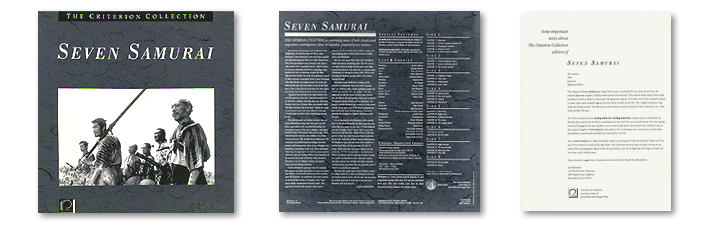 |
|
|
|
|
|
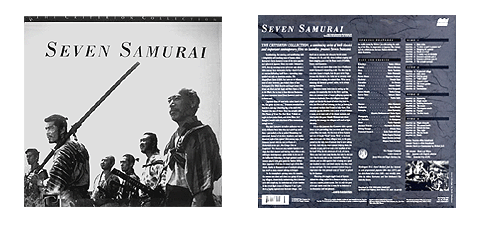 |
||
|
|||
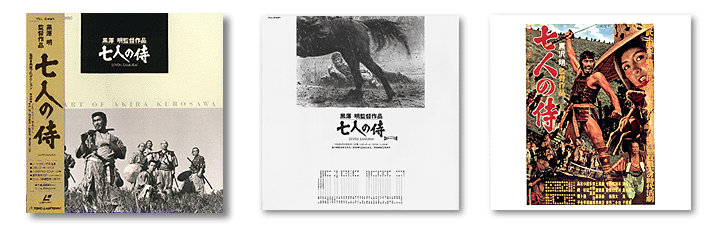 |
|
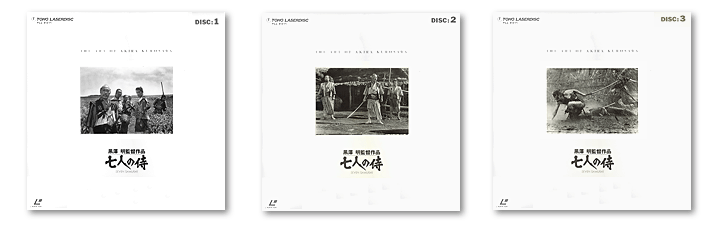 |
|
|
|
|
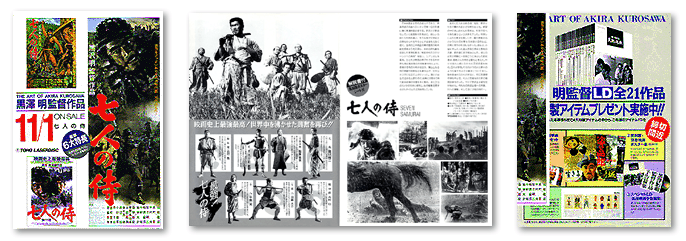 |
|||
|
|||
|
|
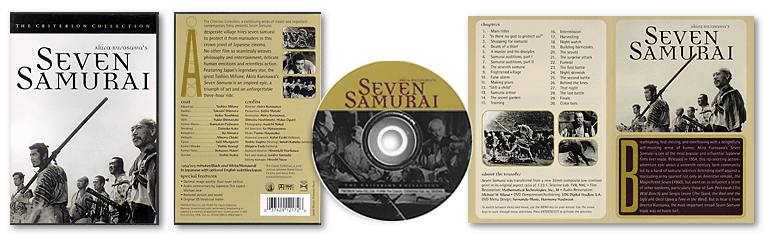 |
|
|
|
|
|
 |
||
|
|||
 |
|
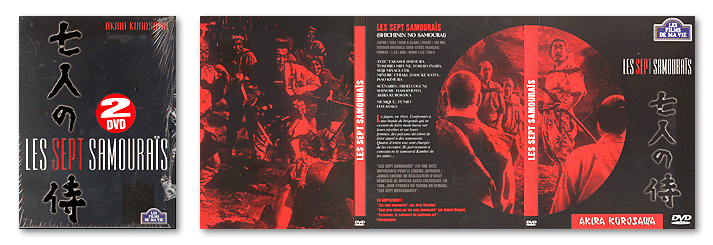 |
||
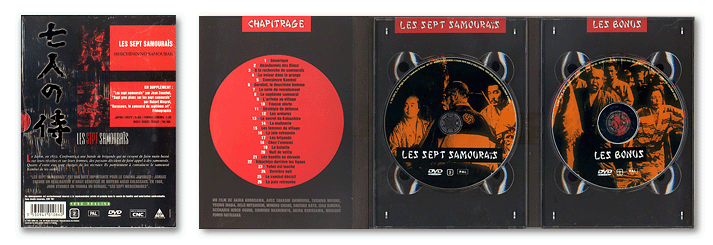 |
||
|
||
|
||
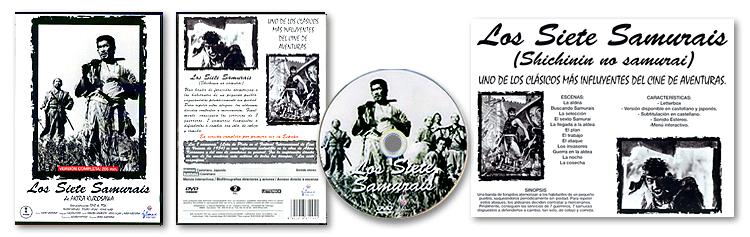 |
|
|
|
|
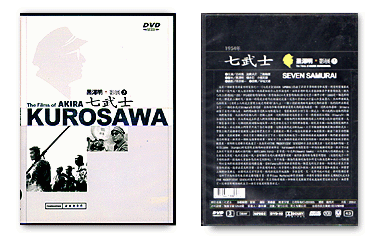 |
|
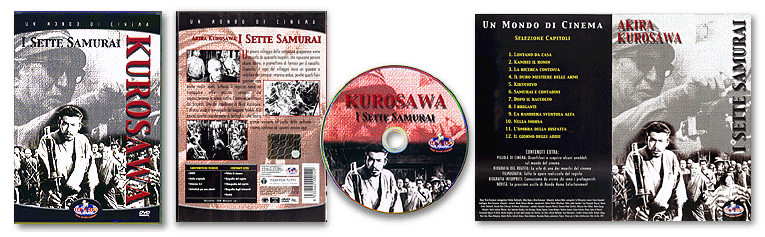 |
|
|
|
|
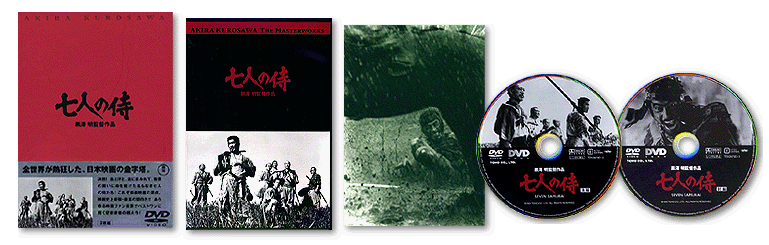 |
|
|
|
|
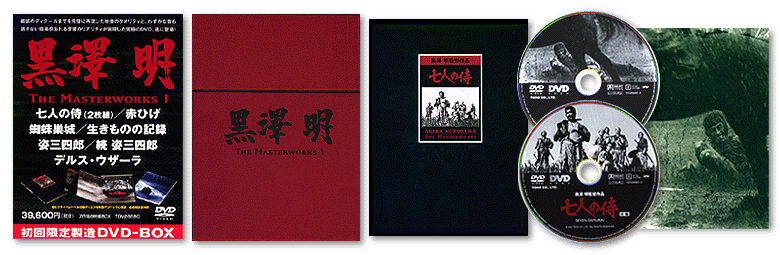 |
|
|
|
|
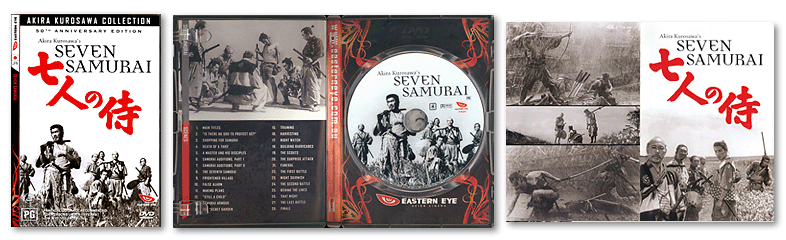 |
|
|
|
|
|
 |
||
|
|||
|
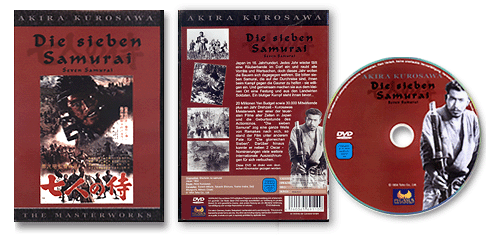 |
||
|
|||
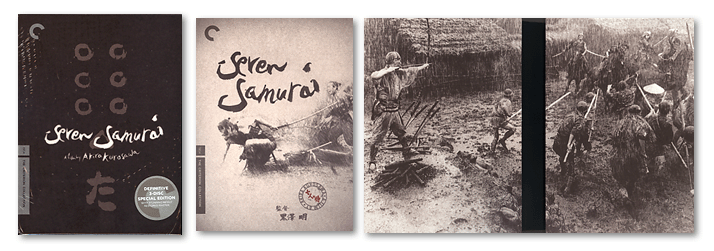 |
|
 |
|
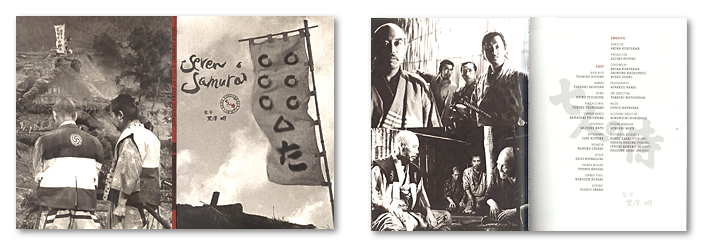 |
|
|
|
|
|
|
 |
||
|
|||
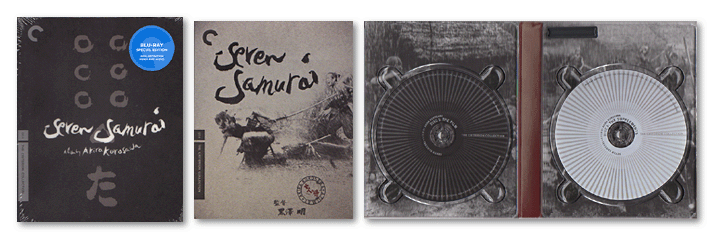 |
||||
|
||||
|
|
 |
|
|
|
|
●本サイトに掲載されているジャケット画像および静止画像にはそれぞれの然るべき製作者・著作者にその権利があります。本サイトは、それらの製作者・著作者からなんらかの指摘および注意を受けた場合には、すみやかに画像・内容を消去するなどの対応をいたします。 ●LD/DVDのチョイスや解説は独断と偏見です。記載事実に誤り等がございましたらメールでご意見お願い致します。 ※本サイトに掲載されている文章の引用・転載は自由です。ただし、著作権は放棄していませんので、引用・転載前にご連絡ください。 ※本サイトに掲載されている文章は、独断と偏見によるまったくの個人的意見が中心となっております。また、本サイト上のデータは、個人的資料によるもので、その正確性・正当性に欠ける場合もございますがご容赦ください。 |
| HOME | ギャラリーコラムへ |